連鎖させる活動

コラボ講義とは?
「語れる」が広がれば
「伝わる」もきっと増える。
コラボ講義は、親元を離れ、児童養護施設や自立援助ホーム、児童自立支援施設など、社会的養護のもとで暮らした経験のある当事者が、大学の講義にゲストとして参加し、自身の体験や思いを学生に語る活動です。
これまでは代表・田中れいかが一人で講義を行ってきました。けれど、全国でさまざまな場所を訪れ、語り、耳を傾けるなかで、こう感じるようになりました。
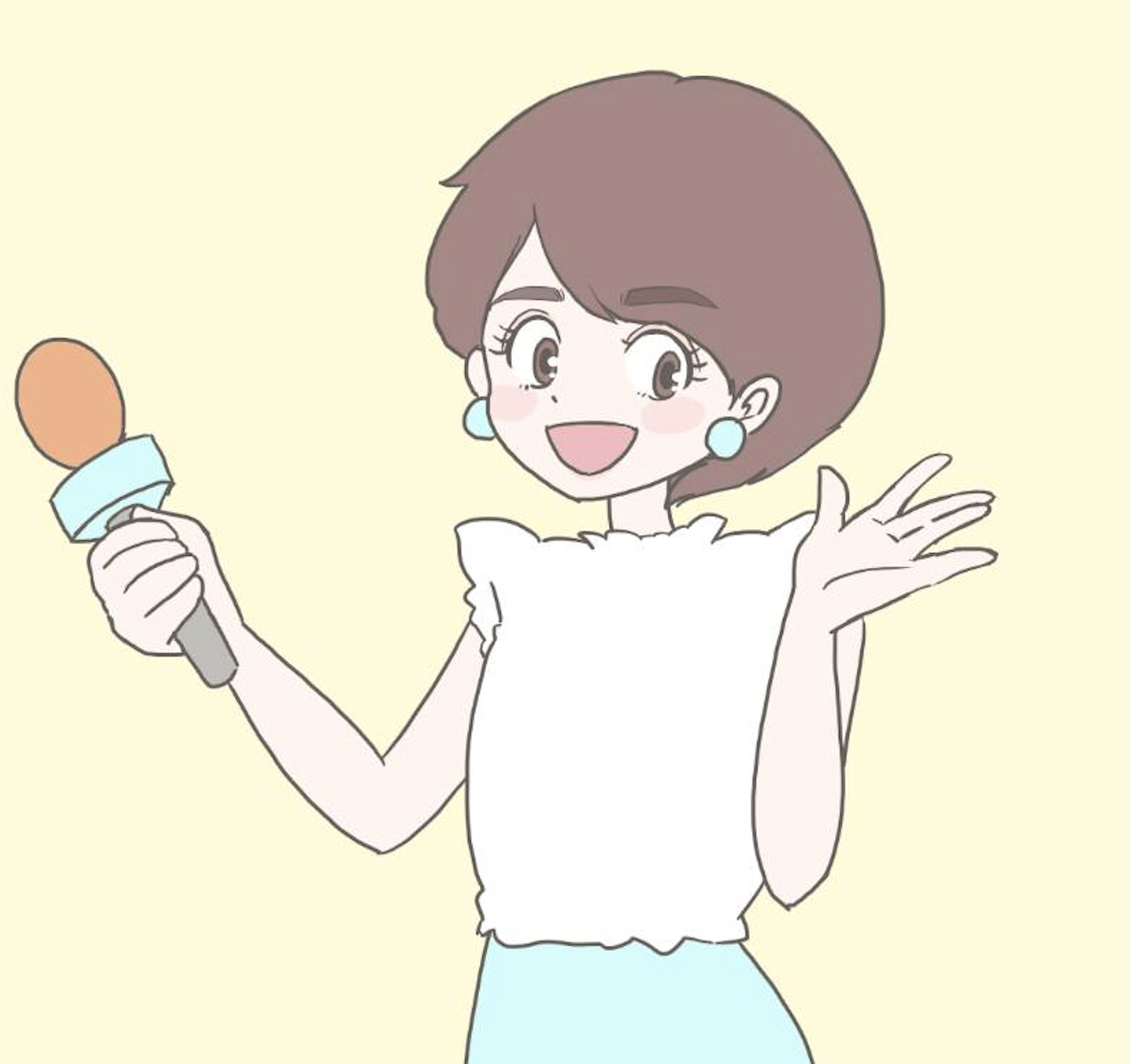
「聞いちゃいけない」と思わせる空気が、まだどこかにある。
でも、語ることは、特別な誰かのものじゃない。どんな経験にも、どんな人にも、自分の言葉で語る力がある。
代表自身は、そう強く思っています。
でもその想いを声高に語る前に、まずはそっと差し出したのが、「ねぇ、一緒に話してくれない?」というひとことでした。
その思いに共感してくれた当事者と田中れいかがともに語るかたちで、「コラボ講義」という取り組みがはじまりました。
なぜ、コラボ講義を行うのか
社会的養護の当事者が声をあげる機会は、いまも限られた人に集中しています。
無償、もしくは非常に低い謝礼で依頼されることも多く、 何度も語るうちに疲弊し、心がすり減って活動から離れてしまう人もいます。
また、語れる人だけが「代弁者」のように見られることで、語る場を求めている人や、まだ言葉にできない人の存在が見えにくくなっています。
たすけあいは、こうした現状にひとつの仮説を立てました。
もっと多くの人が、
自分の経験を
自分の言葉で語れるようになったら
多様な社会的養護の声が広がり、語ることそのものが、
語り手自身の回復や
人生の納得感につながるのではないか?
語るという行為は、ただ誰かに伝えるためだけのものではありません。
自分の過去を見つめ直し、今の自分を受け入れ、「これが私の人生だった」と腑に落とすプロセスでもあります。
たすけあいは、講義という場を通して、こうした語りの土壌を育てていきたいと考えています。
どんな講義をしているの?
講義では、社会的養護の制度や生活についての基本的な説明に加え、自身の体験をもとに語られるリアルなエピソードをお届けします。
- 社会的養護につながる前の家庭環境
- 児童養護施設や里親家庭での暮らし
- 施設を出たあと(進学・就職・孤立の問題)
- 「こんな支援があってよかった」「これは苦しかった」
- 今、当事者として伝えたいこと
届いた感想
※読みやすいように編集しています
自分では経験したことのない内容だったため、理解が難しい部分もあった。けれど、社会的養護のもとでどのような生活が送られているのかを知ることができた。
今回の講義で得たことは、これからの自分にきっと活かせると思う。
今回の講義の中で、「担当の職員が変更することは、親が変わることと同じ」という言葉が印象に残った。
一見、ただの配置換えのように見える出来事も、子どもにとっては心のよりどころを失うほどの影響があるのだと気づかされた。
支援の中で関わる大人の責任の重さと、その信頼を丁寧に築いていくことの大切さを考えさせられた。
私は、社会的養護の存在がどれだけ大切かを改めて感じました。
自分の力だけではどうにもならない状況に置かれたとき、社会が支えてくれる仕組みがあるというのは、社会の可能性そのものだと思ったからです。
スピーカーの紹介
一時保護所、児童自立生活施設での生活を経験。
講義実績:立教大学/聖徳大学 保育科 「社会的養護II」
一時保護所、自立援助ホームでの生活を経験。
講義実績:聖学院大学 心理

2025年度の取り組みとして、スピーカーをしてくれている人たちのインタビュー記事を更新する予定だよ
よくある質問
はい、もちろんです!スピーカーの体験を尊重しつつ、ご希望に合わせたテーマを相談しながら組み立てます。初めてご依頼いただく場合は事前にオンラインで顔わせの機会をつくることも可能です。
はい、もちろんです!単発でも継続でも対応いたします。
スピーカーの同意を得た場合に限り可能です。
はい!田中れいかは、講義のはじめに社会的養護に関する基本情報の説明を担当します。その後は、施設での生活経験について語るスピーカーにマイクを渡し、進行役として講義を進めていきます。
また、スピーカーの話の中で「今、聞いている皆さんが気になったかもしれない」と感じた部分について、その場で質問を投げかけたり、話を深めたりする役割を担います。

